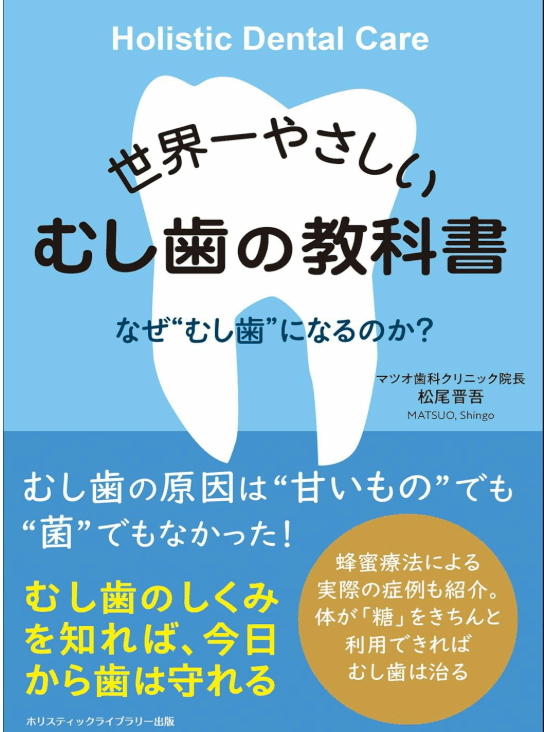「世界一やさしいむし歯の教科書」松尾晋吾(著)のまとめ
書評というか、まとめです。以下のような副題です。
なぜ「むし歯」になるのか?
むし歯の原因は「甘いもの」でも「菌」でもなかった!
体が「糖」をきちんと利用できればむし歯は治る
むし歯の原因は「甘いもの」でも「菌」でもなかった!
体が「糖」をきちんと利用できればむし歯は治る
みなさんは、甘いものをたくさん摂るし、歯も磨かないのに、むし歯にならない人や、甘いものを制限して、歯をきれいに磨いているのに、むし歯になってしまう人を見たことないでしょうか。実は、日常の臨床では、そのような患者さんをたくさん診てきました。そのような場合に、「甘いものを控えましょう」「歯を磨きましょう」「フッ素を塗りましょう」くらいしか言えず、また新たなむし歯をみつけては、削って治療をし、これでいいのかとずっと疑問に思ってきました。
それは、むし歯についての常識が、小さな頃から刷り込まれた間違いであるという主張です。すべて正しいと明言できないものの、おおむね以上のような疑問を解決できる内容でした。私たち歯科医師にとって、衝撃的な内容です。
●日々、臨床でむし歯は菌がつくるというよりも自分の細胞がつくっていると考えたほうがつじつまが合う。
●「糖がむし歯をつくるから、糖を摂ってはダメ」と言われたことはないか。
●むし歯は糖が原因ではなく、そこに菌が絡むことでむし歯になると考えられている。
●むし歯菌が糖を食べたあとの排泄物である乳酸が歯を溶かすと考えられている。
●だから歯科の世界は「糖質制限」信仰に染まっている。
●「糖がむし歯をつくるから、糖を摂ってはダメ」と言われたことはないか。
●むし歯は糖が原因ではなく、そこに菌が絡むことでむし歯になると考えられている。
●むし歯菌が糖を食べたあとの排泄物である乳酸が歯を溶かすと考えられている。
●だから歯科の世界は「糖質制限」信仰に染まっている。
●しかし、むし歯菌は常在菌であり、体にいいとされる乳酸菌。体の細胞が健康であれば、常在菌が悪さをすることはない。
●むし歯を撲滅できないのは原因を間違えているから。
●むし歯を撲滅できないのは原因を間違えているから。
●古代、「歯虫」という伝説上の虫が、歯を内部から溶かしてむし歯をつくると信じられていた。
●18世紀まで、病気になるかどうかは、体の状態次第で、宿主側の健康状態によると考えられていた(宿主説)。
●顕微鏡の発明で歯科学は後退した。宿主説から病原体仮説に変わり、「敵をやっつける発想」から抜け出せなくなった。
●現代人は、むし歯の病原体仮説を刷り込まれ、幼い頃から微生物と砂糖に対する恐怖を植えつけられている。
●18世紀まで、病気になるかどうかは、体の状態次第で、宿主側の健康状態によると考えられていた(宿主説)。
●顕微鏡の発明で歯科学は後退した。宿主説から病原体仮説に変わり、「敵をやっつける発想」から抜け出せなくなった。
●現代人は、むし歯の病原体仮説を刷り込まれ、幼い頃から微生物と砂糖に対する恐怖を植えつけられている。
●本当は、むし歯ができる病的な環境にしているのは、菌ではなく、歯の内部の歯髄で生活する細胞たち。
●歯髄の細胞が病的になると、歯を内部から酸性環境にしてしまう。
●細胞の生活環境の悪化により、つまり自分の体の細胞の「生活苦」によって、やむを得ず歯を壊してしまう(宿主説)。
●歯髄の細胞が病的になると、歯を内部から酸性環境にしてしまう。
●細胞の生活環境の悪化により、つまり自分の体の細胞の「生活苦」によって、やむを得ず歯を壊してしまう(宿主説)。
・つまり、むし歯菌がつくった乳酸はむし歯の原因ではなく、むし歯になった結果、むし歯菌が乳酸をつくってしまうのである。
●歯の中の細胞が健全であれば、歯の中で産生された乳酸は歯の中できれいに処理され、歯は溶けない。
●歯を溶かすむし歯の正体は、糖のエネルギー代謝の障害を起こした低酸素状態の象牙芽細胞。
●歯の中の細胞が健全であれば、歯の中で産生された乳酸は歯の中できれいに処理され、歯は溶けない。
●歯を溶かすむし歯の正体は、糖のエネルギー代謝の障害を起こした低酸素状態の象牙芽細胞。
●本当の犯人は①プーファ(多価不飽和脂肪酸)②エストロゲン(女性ホルモン)③乳酸④噛みしめ⑤スパイクタンパク。
●ちまたの健康情報を鵜呑みにして、糖質制限をしてオメガ3を積極的に摂るのは、もっとも危険。
●コロナワクチン接種がはじまってから、癌やむし歯が増えたのも関連性がある。未接種者もシェディングによってスパイクタンパクの影響を受けるので注意が必要。
●コロナワクチン接種がはじまってから、癌やむし歯が増えたのも関連性がある。未接種者もシェディングによってスパイクタンパクの影響を受けるので注意が必要。
●糖を制限させる歯科衛生士指導がミトコンドリアの糖のエネルギー代謝を壊すことで、元気のない子どもを増やしているかも。
●歯の表面しかフッ素を沈着させないフッ素塗布は、エナメル質内部の脱灰まで修復できないので有効ではないかも。
●歯の表面しかフッ素を沈着させないフッ素塗布は、エナメル質内部の脱灰まで修復できないので有効ではないかも。
●現代人は、「症状を消すことがいいこと」「症状が消えたことが治ったのだ」と勘違いさせられている。それは、細胞の声や叫びをを消し去っている対症療法の医術にすぎない。
●症状が出ないようにする方法として、手っ取り速いのが、エネルギーを低下させて、環境変化に反応しないように、細胞を大人しくさせておくこと。これを健康にいいとはき違えている。
●子どもに砂糖を与えると、大人しくしない、落ち着きがない、動き回る活発な「元気な子ども」になってしまうが、これが本来の子どもの姿。
●今の子どもたちは、姿勢が悪く、呼吸も浅く、じっとして、親の言うことに従順でおとなしい。
●むし歯がないから健康だ!と短絡的に言えない。
●症状が出ないようにする方法として、手っ取り速いのが、エネルギーを低下させて、環境変化に反応しないように、細胞を大人しくさせておくこと。これを健康にいいとはき違えている。
●子どもに砂糖を与えると、大人しくしない、落ち着きがない、動き回る活発な「元気な子ども」になってしまうが、これが本来の子どもの姿。
●今の子どもたちは、姿勢が悪く、呼吸も浅く、じっとして、親の言うことに従順でおとなしい。
●むし歯がないから健康だ!と短絡的に言えない。
●小さい頃から果物や甘いものが好きで、ろくに歯も磨かないのに歯が強くてむし歯ができない人がいる理由は、胎児のときからしっかり砂糖や蜂蜜、果物といった良質な糖を摂って、糖のエネルギー代謝で糖を完全燃焼させていれば歯が強くなるから。
●基礎代謝が低い人は、むし歯ができやすい。日光を浴びながらのウォーキング、ストレッチからはじめよう。
●ミネラル(塩)が不足すると、糖のエネルギー代謝を止めてしまう。
●ミネラル(塩)が不足すると、糖のエネルギー代謝を止めてしまう。
|
|